| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| しのざき しげお | 学芸部 | 学芸部の総括
民俗 |
日本民俗学 |
| 篠﨑 茂雄 | 学芸部長 | ||
| SHINOZAKI SHIGEO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。大学・大学院で社会科教育学(地理学)を専攻したのち、栃木県の高校の社会科教員となり、1999年から県立博物館に勤務しています。伝統工芸、伝統芸能、生産生業、衣食住等生活文化全般(民俗)を担当しています。なかでも野州麻、結城紬、那珂川の漁撈習俗については、詳しく調査研究を行い、企画展図録、調査研究報告書等で紹介しました。これからも栃木県の文化を内外に紹介するとともに、その向上につとめていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・ 「麻」「結城紬」「漁撈用具」「山・鉾・屋台」「伝統工芸」等に関する企画展を担当 ・伝統工芸、伝統芸能、生産生業等に関する普及啓蒙活動 ・主な著書・論文:『栃木民俗探訪』(下野新聞社、2003年)、「アサ利用の民俗学的研究」([『国立歴史民俗博物館研究報告』 187、2014年)ほか ・所属学会:日本民具学会、日本民俗学会、栃木県歴史文化研究会、下野民俗研究会ほか ・その他 帝京大学非常勤講師(博物館経営論)、足利市・栃木市・那須烏山市の文化財専門委員ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| かわら ともき | 学芸部人文課 | 考古(原始) | 日本考古学(原始) |
| 河原 智紀 | 主任 | ||
| KAWARA TOMOKI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県茂木町生まれ。大学では戦争体験者の思考様式に関心を持ち、聞き取り調査を行っていました。卒業後、栃木県の地歴公民科教員として高校に勤務し、2024年度より栃木県立博物館の考古担当となりました。高校での経験を生かし、来館者の皆様にとって分かりやすく、興味深い展示となるよう努めて参ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| あらい けいた | 学芸部人文課 | 考古(古代) | 日本考古学・古墳時代 |
| 荒井 啓汰 | 研究員 | ||
| ARAI KEITA |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県那須烏山市生まれ。大学・大学院で考古学を学んだのち、2023年度から県立博物館に勤務しています。古墳時代、特に横穴式石室の埋葬のしかたなどに関心があります。考古学は、遺跡やそこに残されたモノを通して、人間や社会を明らかにする学問です。栃木県内にも多くの遺跡があり、それらを丹念に調べることで、遥か昔の人間の生活やダイナミックな社会の動きが分かってきます。考古学からとちぎの歴史と魅力をお伝えしていけるように頑張ってまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R06テーマ展「巡回展 栃木の遺跡」 ・R06企画展「死者と生者の古墳時代~下野における6・7世紀の葬送儀礼~」を担当 ・主な論文:「常総地域の箱式石棺からみた古墳時代後半期の埋葬行為」(『考古学研究』第67巻第3号、2020年)、「人骨出土状況からみた横穴式石室の埋葬方法」(『栃木県考古学会誌』第42集、2021年)、「下野地域南部における河原石小口積み横穴式石室の変遷」(『栃木県立博物館研究紀要』第41号、2024年)、『埋葬行為と社会的記憶からみた古墳時代の終焉』(2024年、六一書房)ほか ・所属学会・研究会:栃木県考古学会、日本考古学協会、考古学研究会ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| なかやま まり | 学芸部人文課 | 考古 | 植物考古学 |
| 中山 真理 | 学芸企画推進員 | ||
| NAKAYAMA MARI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。短大・大学で考古学を学んだのち、県内で埋蔵文化財関係の仕事をしていました。2017年から学芸企画推進員として県立博物館に勤務しています。縄文時代の人々がどのように植物を利用したのかについて関心があります。考古学を通して栃木県の魅力を発信してきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| すなかわ よしてる | 学芸部人文課 | 歴史(中世) | 栃木県の中世史 |
| 砂川 恭輝 | 主任 | ||
| SUNAKAWA YOSHITERU |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
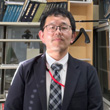
|
栃木県宇都宮市生まれ。大学では考古学、大学院で社会科教育学を学んだ後、栃木県の中学校、高校の教員を経て2023年から県立博物館勤務となりました。博物館では中世分野を担当しています。実物資料と文字資料の両面から栃木の歴史に迫っていけるよう努力していきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・栃木県における中世関係の調査研究 ・R5テーマ展「下野薬師寺と龍興寺 ~鑑真和上とゆかりのある名刹~」を主担当 ・R06テーマ展「藤原秀郷とその末裔たち~語り継がれる史実と伝説~」を主担当 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| いいづか まさし | 学芸部人文課 | 人文課の総括 歴史(近世) |
河川 水運 |
| 飯塚 真史 | 人文課長 | ||
| IIZUKA MASASHI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県佐野市生まれ。大学・大学院で社会科教育学(歴史学)を学んだ後、栃木県の高校の地歴科教員となり、2011年から県立博物館に勤務しています。近世史(主に江戸時代の歴史)を担当しています。なかでも水運・流通・町人文化について興味・関心をもっています。今後も様々な側面から栃木県の歴史文化にせまり、その実像についてわかりやすく紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R05企画展「近代皇室と栃木」、R06テーマ展「武士の装いー館蔵刀剣武具展ー」、R03テーマ展奥羽再仕置四三〇周年記念「徳川家康が下野にやってきた!」、R02特別展示「令和の御大礼」、H29開館35周年記念特別企画展「中世宇都宮氏」、H29企画展「宇都宮藩主戸田氏」、H26企画展「江戸とつながる川の道」等を担当 ・所属学会:栃木県歴史文化研究会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| こやなぎ まゆみ | 学芸部人文課 | 歴史(近現代) | 栃木県の近現代史 |
| 小栁 真弓 | 特別研究員 | ||
| KOYANAGI MAYUMI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県小山市生まれ。鎌倉時代の小山氏に関心を持ち、大学では日本中世史を専攻。 栃木県の地理歴史科教員を経て、2020年度より県立博物館勤務となりました。 当館では明治時代以降の栃木県の歴史を担当し、近代産業や近代建築、近代文学など幅広く対応しています。 近年関心をもって取り組んでいるのが、戦争関連資料の収集と保存です。 県内外の方々から寄せられた軍事・戦争・戦災にまつわる資料や情報を中心に調査研究を進め、 令和7年度夏に特別企画展「とちぎ戦後80年~いま、おやと子で知る 軍隊・戦争と栃木~」を開催します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R03トピック展示「歴史収蔵庫で見つけた!渋沢栄一の足跡」、R03テーマ展「生誕140年野口雨情~童心の詩人と終焉の地・宇都宮~」、R04テーマ展「戦争の“記憶”を引き継ぐ」、R05秋季企画展「近代皇室と栃木~とちぎ御用邸ものがたり~」、R06テーマ展「ちらしも積もれば”宝”の山!~引札が彩る下野の正月~」を担当 ・明治時代以降の栃木県に関する資料の寄贈受け入れ・調査・整理など ・所属学会:栃木県歴史文化研究会 ・その他:宇都宮市文化財審議委員、真岡市文化財調査委員ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| みやた たえこ | 学芸部人文課 | 民俗 | 日本人の観念 |
| 宮田 妙子 | 主任研究員 | ||
| MIYATA TAEKO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
茨城県水戸市育ち。両親は栃木県出身。大学・大学院で日本民俗学を専攻。他県の博物館数館で嘱託職員等として勤めたのち、2007年から学芸嘱託員(民俗)、2012年からは学芸員として県立博物館に勤務しています。当館では、民間信仰、人生儀礼、那珂川の漁撈習俗などを中心に調査・研究、発表をしてきました。さまざまな民俗事象から人々の思いを読み取りたいと考えています。今後も、栃木県の個性を掘り起こすべく調査・研究を続け、多くの方と関わりながらともに発信していきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R04企画展「異界~あなたとふいにつながるせかい~」、R01企画展「昭和ノスタルジー-なつかしい栃木の情景-」、R06テーマ展「昔のこと知ってっけ?~道具を知れば暮らしが見える~」、R05テーマ展「草・木・虫をめぐる栃木の民俗」、H26テーマ展「那珂川の漁撈用具」、H23テーマ展「願い・占い・まじない」、H22テーマ展「くらしの中の装いとしぐさ」などを主担当。 ・主な論文:「「異界」体験アンケートの分析」(『栃木県立博物館研究紀要』41、2024年)、「異界に関わる民具-栃木県の事例から見たメカイ・ホウキ・ミの役割-」(『栃木県立博物館研究紀要』38、2021年)、「倍返しという奉納方法について-栃木県の事例から-」(『神・人・自然』1、「神・人・自然」研究会、2011年)ほか ・所属学会:日本民俗学会、下野民俗研究会、栃木県歴史文化研究会ほか ・その他:大田原市歴史民俗資料館運営委員、とちぎ歴史資料ネットワーク運営委員、帝京大学非常勤講師(博物館資料論)ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| さとう みつひろ | 学芸部人文課 | 民俗 | 民俗 |
| 佐藤 光弘 | 学芸企画推進員 | ||
| SATO MITSUHIRO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。大学では、文学部西洋史学科で、主にアメリカの人種差別について研究しました。その後、栃木県の中学校社会科教諭として勤務、一方で被差別部落について学び人権と差別について追究してきました。2022年度から学芸企画推進員として県立博物館に勤務しています。宇都宮市大谷地区の歴史と文化(特に石材産業の発展と人々の生活)に関心があります。自然と文化が結びついた栃木県ならではの人々の姿を紹介し、皆様の生活に役立てて頂けるよう、調査研究に努めてまいります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R04企画展「異界~あなたとふいにつながるせかい~」、R04テーマ展「栃木の平野の暮らし~稲作~」、R05テーマ展「草・木・虫をめぐる栃木の民俗」、R06テーマ展「昔のこと知ってっけ?~道具を知れば暮らしが見える~」を副担当。R06テーマ展「栃木の畑作~麻・麦・かんぴょう~」を担当。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| ふかさわ まあさ | 学芸部人文課 | 美術工芸 | 日本美術史(仏教彫刻史) |
| 深沢 麻亜沙 | 主任 | ||
| FUKASAWA MAASA |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
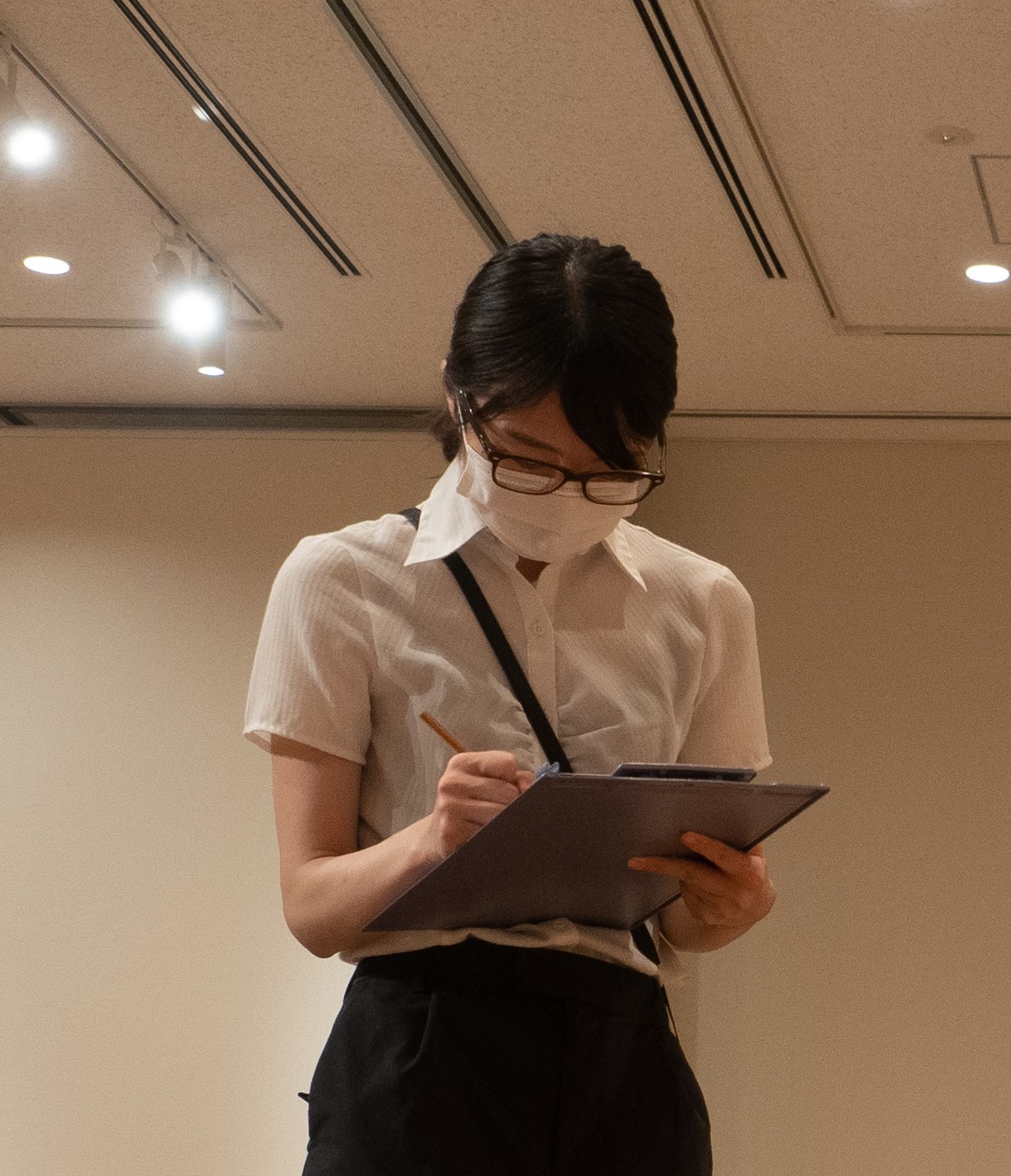
|
岩手県北上市生まれ。大学時代に読んだ仏像の本に夢中になり、大学院から本格的に日本美術史を学び始めました。平安後期の仏像に心惹かれ、京都の浄瑠璃寺九体阿弥陀像など南山城地域(京都府南部から奈良県北部)に伝来した仏像について研究しています。県立博物館には2014年から学芸嘱託員として勤務し、2018年に学芸員に採用されました。県内の仏像や近世絵画の調査・研究を通して、古代から豊かな文化を育んできた栃木県の魅力を美術の面から発信していきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R04開館40周年記念特別企画展「鑑真和上と下野薬師寺~天下三戒壇でつながる信仰の場~」、R02企画展「生誕250年記念 偉大なる無名画家 小泉斐」などを担当。 ・主な論文:「佐貫磨崖仏奥の院大悲窟出土の銅板曼荼羅について―下野における末法思想を背景とした石仏奉納の一遺例―」(『栃木県立博物館研究紀要』 35、2018年)、「鹿沼市医王寺蔵毘沙門天および吉祥天像の体内納入品について(上)(中)(下)」(『栃木県立博物館研究紀要』 32~34、2015~2017年) ほか ・所属学会:美術史学会、仏教芸術学会、栃木県歴史文化研究会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| ひさの かほ | 学芸部人文課 | 美術工芸 | 日本美術史(中近世絵画) |
| 久野 華歩 | 学芸企画推進員 | ||
| HISANO KAHO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県下野市生まれ。大学・大学院で日本美術史を学び、2018年から県立博物館に勤務しています。とくに聖地や名所といった景観を描く絵画に関心があり、これまでは富士山や東海道関連の絵画を研究してきました。最近では、実際の富士登山のようすを描きとめた下野国出身の江戸時代の画人小泉斐についても興味を持っています。信仰や文芸とも関わりあう地域の美術と文化のありさまを紐解いていければと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R02企画展「生誕250年記念 偉大なる無名画家 小泉斐」、R02テーマ展「写山楼~谷文晁一門の絵画学習~」、R06企画展「メジャーもマイナーも大公開!とちぎ江戸絵画の底力~珠玉の上野記念館コレクション~」などを担当。 ・主な論文:「静岡県指定文化財「富士浅間曼荼羅図(富士参詣曼荼羅)」の特質―図様解釈をめぐって―」(『美術史』 185、2018年)、「木村姓時代の小泉斐と水戸藩士たちとの交遊」(『歴史と文化』31、2022年) ・所属学会:美術史学会・栃木県歴史文化研究会ほか ・その他:文星芸術大学非常勤講師(日本美術史Ⅱ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| よしだ たかひろ | 学芸部自然課 | 岩石・鉱物 | 岩石・鉱物 |
| 吉田 貴洋 | 主任研究員 | ||
| YOSHIDA TAKAHIRO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。大学院で海底地形について学び、卒業後、中学校教諭として県内の中学校に勤務しました。2018年より、県立博物館の岩石・鉱物担当として勤務しています。展示や講座・観察会を通して、地学の楽しさを伝えていきたいと考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R03企画展「鉱物と宝石の教室」、R05テーマ展「ぼくらの自由研究~川の地形と石~」、R06テーマ展「地層の剥ぎ取り標本っておもしろい!」を担当 ・講座「火山灰は宝石箱」、観察会「たんぼ物語」を担当 ・所属学会・研究会:栃木地学愛好会(事務局) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| かわの しげのり | 学芸部自然課 | 古生物 | 地質および古生物 |
| 河野 重範 | 主任研究員 | ||
| KAWANO SHIGENORI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
佐賀県生まれ。大学・大学院で地質学と古生物学を学び、新生代の地質と古生物について研究した後、2014年から県立博物館に勤務しています。新生代以降の北関東の大地の生い立ちに興味を持ち、地質学と古生物学の両面から調べています。私たちの住む大地や化石(古生物)に興味や関心をもってもらえるよう、地域移動博物館や県内で進められているジオパーク構想などの活動に関わっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R04企画展「アンモナイトの秘密~太古の海の不思議な生き物~」、H30共催展「タイムトラベル・恐竜世界 わくわく!恐竜展」、同企画展「レッドデータブックとちぎ2018」(展示総括)、H29企画展「大集合!北関東の動植物化石」などを担当 ・河野重範・主森 亘・吉澤時明(2022)栃木県那須烏山市の中新統荒川層群大金層から産出した鰭脚類犬歯化石.栃木県立博物館研究紀要―自然― (39): 1–6. ・主な著書等:『レッドデータブックとちぎ2018』分担執筆(栃木県、2018年)、『栃木県立博物館自然部門収蔵資料目録 (18) 化石 (1) 』(2018年)ほか ・所属学会・研究会:日本古生物学会、地学団体研究会、化石研究会ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| ぬのかわ よしひで | 学芸部自然課 | 地学 | 岩石・鉱物・地質 |
| 布川 嘉英 | 学芸企画推進員 | ||
| NUNOKAWA YOSHIHIDE |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木市在住。以前11年間当館に学芸員として勤務しておりました。その後8年間の教員生活を挟んで、再び当館に勤務することになりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・学生時代のテーマである栃木県内の新生代の地質についてさらに調査・研究を進める。 ・栃木県版レッドデータブック地形・地質分野の調査を行う。 ・県内の地形・地質について、観察会や出前授業を通して普及教育に努める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| ほし なおと | 学芸部自然課 | 自然課の総括 維管束植物(シダ、種子植物) |
森林の植物社会学 |
| 星 直斗 | 学芸部長補佐兼自然課長 | ||
| HOSHI NAOTO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。大学院では森林の植物社会とその環境との関係について研究しました。その後、本県の高校理科教員となり、2007年から当館に勤務しています。県内の全ての維管束植物を対象とし、その実態の記録・研究を行っています。特に、森林がどんな地形にあるのかに関心があります。最近では、本県の植物研究史にも興味を持っています。館外の方々の協力を得ながら、研究者の功績について整理し、とちぎの植物の現状とともに、展示や講座で発信していきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・H30企画展「レッドデータブックとちぎ2018」、R02テーマ展「日光産の標本から学名がついた動植物」、R03企画展「収蔵庫は宝の山!~博物館の資料収集活動~」、R05企画展「花と虫」などを担当 ・イラモミ、ヤエガワカンバ、クロビイタヤなど国内で希少な樹木や、コウホネ類(水草)などの調査 ・主な著書等:『レッドデータブックとちぎ2018』分担執筆(栃木県、2018年 )ほか ・所属学会・研究会:日本生態学会、植生学会、栃木県植物研究会など ・その他:那須平成の森生物多様性モニタリング等業務専門家ヒアリング会合委員ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| やまもと こうへい | 学芸部自然課 | 維管束植物を除く植物・菌類 | 菌類・地衣類・変形菌類・藻類・蘚苔類を担当 専門は冬虫夏草・地下生菌の分類学 |
| 山本 航平 | 主任 | ||
| YAMAMOTO KOHEI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
京都府京都市生まれ。大学・大学院ではアツギケカビ目菌類の系統分類・生態について研究しました。県立博物館では、2017年から3年間学芸嘱託員として勤務し、2021年から学芸員として勤務しています。普段は見過ごされやすい菌類ですが、意識すれば、様々な生物が菌類と関わり合いながら生きている様子が見えてきます。栃木県の菌類の多様性を解明するためには、少しでも多くの方に菌類へ関心を向けてもらう必要があります。そのために、研究成果の発信・普及活動に積極的に取り組みたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R01テーマ展「冬虫夏草」、R02トピック展示「栃木県で見つかった新種の冬虫夏草 クサイロコメツキムシタケ」、R05テーマ展「地中に生えるキノコ~トリュフとその仲間たち~」などを担当 ・主な著書・論文・総説:「レッドデータブックとちぎ2018」分担執筆(栃木県、2018)、「Taxonomic study of Endogonaceae in the Japanese islands: New species of Endogone, Jimgerdemannia, and Vinositunica, gen. nov.」(Mycologia、2020)、「日本産地下生菌の分類学的研究史」(Truffology:日本地下生菌研究会会報、2018)ほか ・所属学会・研究会:日本菌学会(幹事)、日本冬虫夏草の会(理事)、日本地下生菌研究会(編集長)、栃木県きのこ同好会(事務局長)ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| いがり あさ | 学芸部自然課 | 植物 | 植物・菌類 |
| 猪狩 あさ | 学芸企画推進員 | ||
| IGARI ASA |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。2021年4月より県立博物館に勤務し、主に植物標本の整理をしています。博物館で調査のために採集した標本のほかに、個人で研究されていた方のものや明治・大正の頃の学生の採集したものと、さまざまな標本に出会います。標本を必要とする人がいつか現れた時に役立てるよう整理に取り組んでいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・植物標本の整理 ・展示、観察会、講演会等のサポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| みやけ あきこ | 学芸部自然課 | 植物 | 植物・菌類 |
| 三宅 晶子 | 学芸企画推進員 | ||
| MIYAKE AKIKO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県宇都宮市生まれ。2021年10月より勤務しています。仕事を通じて感じたことは、博物館は知識の宝庫であるということです。この宝庫の魅力を伝えるお手伝いができたらと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・植物や菌類の標本の作製と整理 ・展示・観察会・講演会等のサポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| くりはら たかし | 学芸部自然課 | 昆虫 | 専門はカミキリムシの系統分類学 |
| 栗原 隆 | 主任研究員 | ||
| KURIHARA TAKASHI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
千葉県松戸市生まれらしいですが、すぐに東京都へ転居。大学院で昆虫の系統分類学を学び、東アジアのリンゴカミキリを研究しました。2011年4月から博物館で勤務。現在は栃木県の昆虫相や、サクラやモモを枯らしてしまう外来種クビアカツヤカミキリを調査しています。子どもたちと昆虫観察や標本づくりをするのが大好きです。昆虫好きのみんなが博物館に来てくれるのを待っています! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・H30企画展「レッドデータブックとちぎ2018」、H28企画展「日光の昆虫」などを担当 ・主な著書等:「レッドデータブックとちぎ2018」分担執筆(栃木県、2018年)、「日本産コガネムシ上科標準図鑑」分担執筆(学研教育出版、2012年)、「日本産カミキリムシ」分担執筆(東海大学出版会、2007年)ほか ・所属学会・研究会:日本昆虫学会、日本甲虫学会、とちぎ昆虫愛好会ほか ・その他:渡良瀬遊水地モニタリング検討委員会委員、那須塩原市動植物調査研究会委員ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| みなみや ゆきお | 学芸部自然課 | 昆虫を除く
無脊椎動物 |
ミミズやカタツムリ、エビ・カニ、ダンゴムシなどを担当、専門はミミズ分類学 |
| 南谷 幸雄 | 主任研究員 | ||
| MINAMIYA YUKIO |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
東京都立川市生まれ。幼い頃から生き物好きで、大学の博士課程ではミミズ系統分類について研究しました。2016年から県立博物館に勤務しています。ミミズやダンゴムシなどの身近な無脊椎動物さえ、どんな種類が県内のどこに分布するのかといった基本的な調査が進んでいません。そこで、見かけた無脊椎動物は可能な限り採集して、標本として保存しています。さらに、子どもたちに生き物への興味を持ってもらえるよう、講座や観察会にも力を入れています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・最近の展示 R05企画展「甲殻類ワールド~エビ、カニ、フジツボ、ダンゴムシ、ミジンコ & カブトエビ~」、R04テーマ展「いまも生きるアンモナイトのなかま〜オウムガイ、そしてイカ、タコ〜」、R03テーマ展「ダンゴムシ」などを担当 ・最近の主な論文等: Sato, C. et al. (2023) Origin and diversitication of pheretimoid megascolecid earthworms in the Japanese Archipelago as revealed by mitogenomic phylogenetic. Molecular Phylogenetics and Evolution 182: 107735. Seto, A. et al. (2022) The complete mitochondrial genome sequences of Japanese earthworms Metaphire hilgendorfi and Amynthas yunoshimensis (Clitellata: Megascolecidae). Mitochondrial DNA part B 6(3): 965–967. 南谷幸雄 (2024) 栃木県初記録のクモマハエトリ. Kishidaia (124): 41–42. 南谷幸雄 (2024) 栃木県初記録のメスジロハエトリ. Kishidaia (124): 42–43. 南谷幸雄他 (2023) 栃木県におけるホウネンエビの分布情報の追加. インセクト 74(2): 126–127. 南谷幸雄 (2023) 青いアメリカザリガニを野外で採集. インセクト74(2): 145. 南谷幸雄他 (2022) 栃木県の大型鰓脚類(節足動物門:甲殻亜門:鰓脚綱)の分布. 栃木県立博物館研究紀要―自然― (39): 31–43. 南谷幸雄・田中邦幸 (2022) 栃木県初記録の外来淡水巻貝ヒロマキミズマイマイ. 栃木県立博物館研究紀要―自然― (39): 45–48. ・主な著書等:『土の中の生き物たちの話』分担執筆(朝倉書店、2022年)『実践土壌シリーズ:土壌生態学』分担執筆(朝倉書店、2018年)、『レッドデータブックとちぎ2018』分担執筆(栃木県、2018年)ほか ・所属学会・研究会:日本土壌動物学会、日本貝類学会、日本蜘蛛学会ほか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| おがさわら ゆう | 学芸部自然課 | 脊椎動物 | 哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類を担当 |
| 小笠原 佑 | 主任研究員 | ||
| OGASAWARA YU |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
岩手県北上市生まれ。大学では,八丈島産のトビウオの染色体分析を行いました。卒業後宇都宮市内の中学校に1年,小学校に10年勤務しました。2021年より,県立博物館で脊椎動物担当として勤務しています。県内を中心に脊椎動物の調査を行い,その魅力を伝えていけたらと考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・R04テーマ展「いま知ってほしい栃木の外来生物」の一部を担当 ・観察会「モリアオガエルの観察会」、講座「豚足で骨格標本をつくろう!」を担当 ・脊椎動物の調査 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| うすい かすみ | 学芸部自然課 | 動物 | 昆虫 |
| 薄井 香淑 | 学芸企画推進員 | ||
| KASUMI USUI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
栃木県那須塩原市生まれ。2025年8月より勤務。幼い頃から、野山や田畑で生き物をみつけて捕まえたり絵を描いたりと、自然の中で遊ぶのが好きでした。生き物がどんな場所にいて、人とどう関わって生きているのか関心があります。変わりゆく今の自然を記録し、栃木県の未来に継承すべく、標本の作製や整理に取り組みたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・昆虫標本の作製 ・展示や講座、観察会、野外調査等のサポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 所属・職名 | 博物館での担当 | 専門・調査研究・担当分野 |
|---|---|---|---|
| いのうえ こういち | 学芸部自然課 | 動物 | 動物全般
(主に脊椎動物)を担当 |
| 井上 晃一 | 学芸企画推進員 | ||
| INOUE KOICHI |
| 自己紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
宇都宮市生まれ。県立博物館には2006年~2011年に(主に)脊椎動物担当の学芸嘱託員として勤務、2021年7月より学芸企画推進員として勤務しています。永く後世に残せるよう、丁寧な標本づくりを心掛けていきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
【主な活動内容】
・哺乳類・鳥類の骨格標本の作製 ・展示、観察会、講演会等のサポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
