ヘビ類の行動・生態に関する世界的な研究者である京都大学大学院理学研究科の森哲教授に学生時代から現在に至るまでの研究・活動について、講演していただきました。
森先生の京都大学芦生研究林での調査活動に始まり、研究者として、沖縄、マダガスカル、アジア各国へとフィールドを広げ、国際的な研究チームを組んで活躍されている様子が語られました。
テーマ展「ヘビなんて、キライ!」では、宮城県金華山のヤマカガシについて少し触れています。それに関連して、講演会の中で興味深かったのは、ヤマカガシは自身の頸部に毒を持っているか持っていないかを把握しているらしい、ということです。
毒牙から出る毒とは別に、ヤマカガシは頸線毒を持っています。これは、皮膚が傷つき破れることで出てくる毒です。この頸部に入っている毒は、ヤマカガシ自身の力で作り出すことはできません。これは研究の結果、ヒキガエルに由来する毒で、ヒキガエルを食べることで取り込んでいることが判明しました。宮城県の金華山にはヒキガエルがいません。そのため金華山に生息するヤマカガシは頸部に毒がないのです。
金華山でつかまえたヤマカガシを二つのグループに分けます。ひとつは頸部に毒がないグループ。もうひとつは、ヒキガエルを食べさせ頸部に毒を蓄えさせたグループ。頸部に毒がないグループは、外敵の攻撃に対し逃げる行動を多くとるのに対し、頸部に毒を蓄えたグループは、首曲げや首の打ち付けなど威嚇する行動をとる頻度が高くなるそうです。こうした行動の違いから、ヤマカガシは自身の頸線毒の有無を把握していることがうかがえます。
また、森先生のチームは、中国にいるヤマカガシの仲間が、ヒキガエルではなく、ホタルから毒を取り込んでいるのを発見したそうです。こうした発見ができたのも、研究チームに米国の化学の専門家を交えていたことが大きかったそうです。
他にも、沖縄でのヒメハブ調査、アカマタのウミガメの子の捕食、マダガスカルのヘビのお話など盛りだくさんでした。
(自然課 井上)
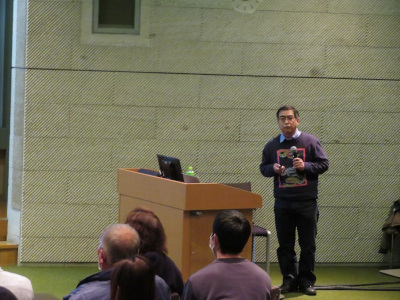
コメント